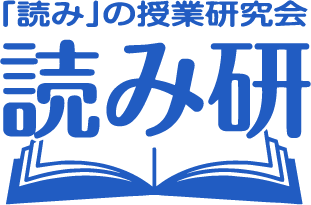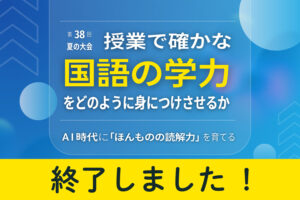第38回 夏の大会、担当者の意気込みを紹介します!

いよいよ開催が迫ってきた読み研・第38回 夏の大会。
今も各分科会・講座を担当する先生方が入念な準備を進めています。今回は、担当者の先生方の意気込みをご紹介します。
参加を迷われている方はもちろん、初めて夏の大会に参加されている方、何度も参加されている方にも、夏の大会の魅力を感じていただければと思います。
8月23日(土)
◆記念講演 🎥
- 授業で確かな国語の学力を身につけさせていくための方法
—AI時代に「ほんものの読解力」を育てる—
講師:阿部 昇(秋田大学 名誉教授)
―使用予定教材:「ちいちゃんのかげおくり」(あまんきみこ)小3・「『鳥獣戯画』を読む」(高畑勲)小6・「作られた『物語』を超えて」(山極寿一)中3ほか

1900年(明治33年)に「国語」という教科が誕生してから125年が経ちますが、いまだに国語の授業で「どのような力・学力を育てるのか」は明確ではありません。子どもたちは「国語で何を学んでいるのかよくわからない」「力がついているのかわからない」と感じています。
この状況を改善するためには、国語の学力の正体、その「具体」を明らかにする必要があります。国語は、指導案の「目標・ねらい」を見ても抽象的で曖昧です。「国語の学力」を理念的・抽象的な表現ではなく、具体的な学力として示す必要があります。
国語の学力にはさまざまな要素がありますが、中心となるのは「読解力」です。そして、読解力を身につけるための鍵が「読む方法」です。子どもは「読む方法」を知り、それを使いこなせるようになることで、国語の学力を着実に伸ばしていきます。
この「読む方法」の重要性は、AI時代においてさらに高まっています。AIが示す答えには事実に基づかない内容(ハルシネーション)が紛れ込むこともあります。それらを見抜くためにも、これまで以上に質の高い「読む方法」が不可欠です。
では、国語の授業ではどのような「読む方法」を育てればよいのでしょうか。
本講演では、「物語・小説」「説明文・論説文」の授業を通して、どのような「読む方法」を育てればよいのかを、教科書教材を例に具体的に提案します。ぜひご参加ください。
◆《物語・小説》ワークショップ的分科会Ⅰ
—確かな国語の学力を身につけさせる物語・小説の授業
(【対面】A・Bより一つを選択【配信】Aを配信🎥)
【A】 入門講座 🎥
―教材「一つの花」(今西祐行)小4・「少年の日の思い出」(H・ヘッセ)中1 を使って
担当:鈴野 高志(茨城・茗溪学園中学 高校)
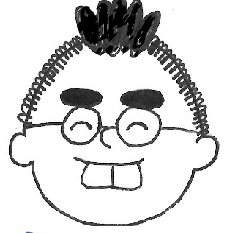
「一つの花」も「少年の日の思い出」も、長きにわたって教科書に掲載されてきた教材であり、ストーリーや登場人物のセリフなどが多くの人たちの心の中に残っていることの多い作品でもあります。
では一方で、それらの作品の学習をとおしてどのような国語の力をつけたのか、――そのことについてはあまり覚えていない方も多いのではないでしょうか。
この講座では、読み研がこれまで追究してきた物語・小説を読む方法について、授業形式での実践を交えながら、特に読み研大会に初めて参加する皆さん向けにご紹介していきます。
「一つの花」をさらっと読んだからすぐ戦争について調べる、とか「少年の日の思い出」をざっと読んだからすぐ蝶について調べたり、コレクションの思い出について発表し合ったりするというような活動に走ってしまうのではなく、作品をしっかり読んで、その後にも生かされる国語の力を子どもたちにつけさせるにはどうしたらよいのかということを示すことができればと考えています。
たくさんの方のご参加をお待ちしています!
【B】発展講座
―教材「たずねびと」(朽木祥)小5・「ヒューマノイド」(伊坂幸太郎)中2 を使って
担当:熊添 由紀子(福岡・八女市立南中学校)

物語・小説の構造よみでまず着目するのが、事件の最大の節目であり主要な事件が決定的となるクライマックスです。 そして、このクライマックスへの着目の際にぜひ指導したいのがクライマックスに向けて仕掛けられている「伏線」です。
「伏線」はクライマックスに収束し、その解決(または破局)が作品のテーマを浮かび上がらせます。
この分科会では、クライマックスと伏線の関わりをどのように指導すればいいのか、また、子どもたちにどのようにして確かな「読みの力」をつけていくのか、小五教材「たずねびと」と中二教材「ヒューマノイド」を使って、参加者の皆様との演習を交えながら提案していきます。
新教材「ヒューマノイド」は、いくつかの伏線が重層的に関わり合いながらクライマックスに収束するという特徴を持つ作品です。
夏休み明けの授業が待ち遠しくなるような分科会にしたいと思いますので、多くの方々の参加をお待ちしています。
◆確かな国語の学力を身につけさせる テーマ別講座
(【対面】A・Bより一つを選択【配信】Aを配信🎥)
【A】 俳人・熊谷尚による「句会」授業の作り方 🎥
担当:熊谷 尚(秋田・秋田市立下新城小学校 校長)

俳句の愛好家たちは、「句会」を開いて互いに研鑽を深めます。句会では、それぞれが作った俳句を読み合い、どの句がよいかを選び、感想等を述べ合います。 句会は「鑑賞」と「批評」が一体となった言語活動そのものなのです。これを国語の授業に持ち込まない手はありません。
本講座では、参会者の皆様に実際に「句会」を体験していただきます。 その中で、作句指導の〝いろは〟や、俳句鑑賞指導のポイントなどをお伝えできれば、と考えています。
句会は、小・中・高の校種を問わず国語の授業に取り入れることが可能です。児童生徒が生き生きと取り組む中で、確かな国語の学力を育むことにつながる俳句の授業づくりについて、参会者の皆様と共に考える70分間にしたいと思います。 どうぞ、奮ってご参加ください。
【B】高校・大学の「入試」を見通した授業
担当:梅田 浩行(長野・佐久市立東中学校)・建石 哲男(神奈川・関東学院六浦高校)

建石 哲男
私たち教員は、教科書だけでなく、入試問題の指導も求められます。では、「読み」の授業研究会が提起してきた読みの方法と、入試問題とはどう繋がるのか、そんなことを考えていく講座です。
実際の入試問題を扱いながら、さらに有効な読みの方法を確認していくという内容です。説明的文章の高校入試問題と、小説の大学入試問題を主な題材にしながら考えていきます。
8月24日(日)
◆《物語・小説》ワークショップ的分科会Ⅱ
—確かな国語の学力を身につけさせる説明文・論説文の授業
(【対面】A・Bより一つを選択【配信】Aを配信🎥)
【A】入門講座 🎥
―教材「すがたをかえる大豆」(国分牧衛)小3・「時計の時間と心の時間」(一川誠)小6・「クマゼミ増加の原因を探る」(沼田英治)中2を使って
担当:町田 雅弘(茨城・茗溪学園中学 高校)

「説明文・論説文の授業」入門講座を担当します、町田雅弘と申します。
「先生、今日の授業は面白かったなー」と生徒に言われる授業を目指していますか? 「ああ、そうか!」「わかった!」という知的な興奮を感じる授業はきっと「面白い」はず。
「この子どもは、読解力がついてきたな」と思える授業を目指していますか? 「読みの方法」を整理して子どもたちに伝えられる授業はきっと「力をつけられる」はず。
説明文・論説文の授業を面白くさせる工夫、力をつけさせる工夫を、たくさん用意してみました。 ぜひ、大勢の方にご参加いただきたいと思っています。
【B】発展講座
―教材「『不便』の価値を見つめ直す」(川上浩司)中1・「水の東西」(山崎正和)高1を使って
担当:岸 あゆり(神奈川・北鎌倉女子学園中学 高校)・渡邊 絵里(福岡・久留米市立宮ノ陣中学校)

渡邊 絵里
最近は便利なAIを使いこなしている子どもたちも多いと思います。ですが、AIの出す答えは本当に正しいとは限りません。AIは根拠が誤ったまま答えを出す危うさもあります。
この講座では吟味よみを通して、教材をクリティカルに読み解きます。 根拠をもって正しく文章を読み解き、物事を批判的に考察する力を身につけられるような授業について、先生方と一緒に検討したいと思います。
◆全体模擬授業 🎥
- 確かな国語の学力を身につけさせる「白いぼうし」(あまんきみこ)小4の授業
授業者:大庭 珠枝(秋田・由利本荘市立東由利小学校 校長)

光村図書小学校四年生の教科書に長きにわたって採用されているファンタジー教材「白いぼうし」。読み研の全体模擬授業で取り上げるのは初めてです。
自分たちで学習課題を設定して読んでいく中で、人物像を捉えたり伏線を発見したりする楽しさを、子どもたちの思考の流れを体感しつつ味わっていただけたらと思います。
読み研の大会に初めてご参加の方も、複数回ご参加くださっている方も、ぜひ子ども役としてご参加ください。お待ちしております。
一つひとつの講座に込められた担当者の想いを、ぜひ会場で直接感じてください。ご参加を心よりお待ちしています!
プロフィール
- 2026.01.28関西地方 2026年3月20日(金・祝日)読み研 関西サークル 学習会
- 2026.01.22春の研究会2026年3月28日(土)「春のスタート講座」開催のお知らせ
- 2025.12.21冬の研究会第40回冬の研究会が本日終了しました!
- 2025.11.06読み研通信『読み研通信』156号が出ました!(無料配信)