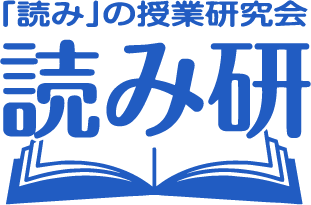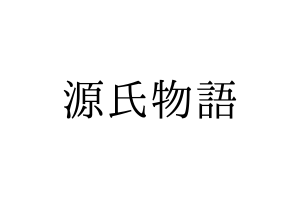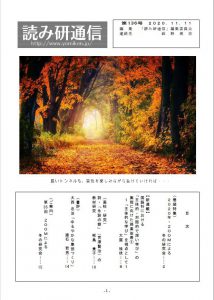読み研春の学習会in八女
3月27日(土)の午前中に、おりなす八女研修棟にて、春の学習会を行うことに致しました。 緊急事態宣言が解除されたとはいえ、まだまだ心配な状況ではありますが、換気や消毒などの感染対策をできる限り行い、参加される先生方にとっ […]
『読み研通信』137号が出ました!(無料配信)
お待たせしました!『読み研通信』137号が出ました。お申込みについてはこのページの最下部をご覧ください。 【主な内容】 *〈巻頭論文〉読み研冬の研究会を受けての実践的考察(臺野芳孝) *〈連載〉国語科における「主体的・対 […]
第35回 読み研 冬の研究会の報告
2020年12月26日(土)に「第35回 読み研 冬の研究会」が開催されました。コロナ禍の中ではありましたが、状況を鑑み、Zoomにての開催となりました。おかげさまで、168名の方に参加していただき無事終了することができ […]
読み研関西サークル春の学習会
「言葉による見方・考え方」を鍛える国語の授業づくり 新学期からの楽しく力のつく国語の授業 コロナ禍で先の見通しのつかない情勢のなか、いつもとは違う仕事にストレスを感じる毎日です。子どもたちも、新しい学習スタイルに慣れ […]
ゲームで、子どもの語彙を増やす②
1 私は誰でしょうゲーム 1人が親になり、小さなホワイトボードに言葉を書きます。残りの子どもが質問をし、答えを聞いて、親が書いた言葉を当てるというゲームです。 例えば、親が「バナナ」と決めます。親以外の子どもたちが「 […]
ゲームで、子どもの語彙を増やす
子どもの語彙を増やしたいと思っています。そのための方法はいくつもあると思いますが、基本は授業の中で文章をしっかり読み、言葉や文の意味を理解し、類語・対義語・例文づくり等の指導も行いながら、語彙を広げていくことだと思います […]
ゲームで、主語・述語・修飾語を学ぶ
小学校では、主語や述語などのはたらきや使い方を少しずつ学習することになっていますが、なかなか定着しません。特に修飾語の指導は難しいというか、子どもには分かりにくいようです。若いころ、学年の先生にそんな悩みを相談すると「ゲ […]
『読み研通信』136号が出ました!(無料配信)
お待たせしました!『読み研通信』136号が出ました。お申込みについてはこのページの最下部をご覧ください。 【主な内容】 *〈巻頭特集〉2020年・Zoomによる冬の研究会 *〈新連載〉国語科における「主体的・対話的で深い […]
2020 長野読み研大学習会のご案内
コロナ禍で例年とは違った情勢のなか、10年続いてきたこの会をどうすべきかたいへん迷いましたが、ほぼ例年の人数を想定し、感染対策をとりながらだったら安全だろうとの見通しのもと、対面での学習会を実施することにいたしました。 […]