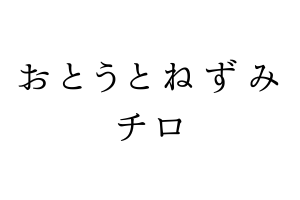小学校 物語の教材研究 (東書・小一)「おとうとねずみ チロ」(もりやまみやこ)を読む その3
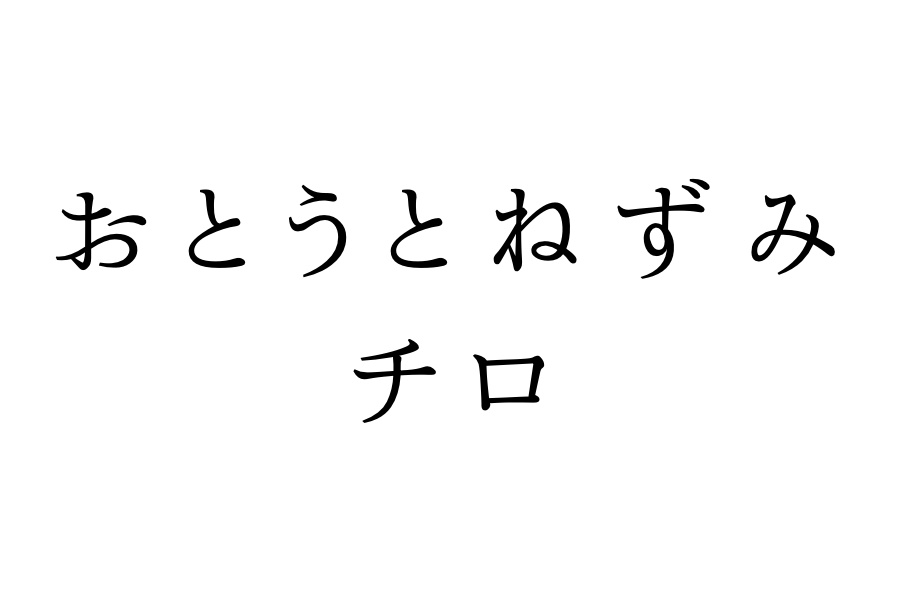
5「あ、り、が、と、う。」の読み
〈四場面〉の最後は次のようである。
そして、「ありがとう。」が きえるのを まって、もう 一ど、こんどは ゆっくり いいました。
「あ、り、が、と、う。」
チロは、「ありがとう」を繰り返す。繰り返しは、チロのうれしい気持ちやおばあちゃんへの感謝の気持ちの強調でもある。それだけチロは、チョッキを編んでもらえたこと、さらには自分のことをおばあちゃんが忘れないでいてくれたことがうれしかったのである。
さらには、その言葉をゆっくりと言うところにもチロの気持ちを読みとることができる。うれしさや感謝の気持ちが大きいからこそ、それをきちんと丁寧に表そうとしているのだ。ゆっくりと言うことで、チロがおばあちゃんに自分の気持ちをきちんと伝えようとしていることもわかる。
「ありがとう」と「あ、り、が、と、う」はどう違うのだろうか。最後の「あ、り、が、と、う。」をチロが大きな声で叫んだとは書かれていない。しかし、「あ、り、が、と、う。」と、それぞれの音の後に読点が入っていることで、一音一音を区切りながらチロが言っていることがわかる。一音一音区切りながらということは、一音一音を大きな声を出して言っているからである。チロは、普通の声の大きさで「ありがとう」と言っているのではない。大きな声で叫んで(チロは大きな声だからおばあちゃんのところに届くと思っている)、なおかつゆっくりと言っているのである。だから、一音一音を区切りながら、叫んでいることになる。
「あ、り、が、と、う。」は、どんなふうに言われたのか、子どもたちに動作化させながら考えさせてもよいだろう。
6 作品のユーモア
チロは、自分の声がおばあちゃんに届いたと思っている。こだまとなって、声がだんだん小さくなっていったのを、おばあちゃんのところに声が飛んでいったと思っている。だから、おばあちゃんからしましまのチョッキが届いたと思っている。このチロの姿は、ほほえましく、そしてちょっとユーモラスである。この話のいちばんの魅力は、ここにあるといってよいだろう。
「おかのてっぺんの木に立つと、たにをはさんで、たかい山が見え」、「おばあちゃんのうちは、あの山のずっとむこうがわに」ある。
川をはさんだ向かい側といった距離ではない。普通に考えれば、とても声の届く距離ではない。
しかし、チロは自分のチョッキも編んでほしいから、何とかおばあちゃんのところに声を届けようと必死である。その一生懸命なところをほほえましく、ユーモラスに感じるのである。
ただ、小学1年生の子どもたち、みながみなチロの行動をユーモラスにとらえられるかと言えば、難しいかもしれない。
チロの声が本当におばあちゃんのところに届いた、そう思う子どももいるだろう。そのような子どもの考えを、無理に否定する必要はない。
声が届いたと思う子どもと声が届くのは無理と読む子どもの両方があってよい。
チロは、何とかおばあちゃんに声が届いて欲しいと思っているのだから、その必死さが奇跡を起こして、おばあちゃんのところにチロの気持ちが伝わったのだという考えも、授業の中では許容すべきだと考える。
その一方で、とても声が届く距離ではない。でも声が届いたと思っているチロはかわいらしいし、ちょっと面白い。そう考える子どももいる。
子どもたちの受け止めは、二様でよい。ただ、チロ自身は声が届いたと思っているという読みは、しっかり抑えておきたい。
先にこの話のクライマックスを「おばあちゃあん、ぼくはチロだよう。しましまのチョッキ、ありがとう。」のところにするとしたが、ここまで述べてきたことからも分かるように、この作品は、チロがチョッキを編んでもらったという話ではない。それならば、クライマックスは〈三場面〉のチョッキが届くところとなる。しかし、それでは、チロの声がおばあちゃんに届いて、チロの願いどおりにチョッキが届いたことになり、この話の面白さが見えてこない。
この話の面白さは、チロが丘の上から大きな声で叫び、おばあちゃんに声を届けられると思うところにある。
クライマックスをめぐっては、〈三場面〉のチョッキが届くところと〈四場面〉の丘の上から「ありがとう」を言うところで意見が分かれるかもしれない。チョッキを編んでもらえた話と読むか、丘の上から叫ぶ声がおばあちゃんに届いたとチロが思う話と読むか、どちらの方が面白いか、子どもたちに考えさせてもよいかもしれない。
7 同化する読みと異化する読み
チロに寄り添って、チロと同じ目線に立って読んでいく読み方が、同化の読みである。チロの身になって、チロの気持ちになって読み進める読みである。そのような読みをすると、おばあちゃんのところに声が届いたという読みになっていく。
チロをちょっと突きはなして読むのが異化する読みである。チロは字が書けない。この作品を授業で学習する頃の小学校1年生は、ひらがなやカタカナが書けるようになっている。つまり、字が書けないチロを子どもたちは自分たちよりももう少し幼いものとみることになる。この作品の読みの過程では、チロに同化して読む面と、チロを少し突きはなして読む面の二つがある。チロを突きはなす(異化する)読みができるほど、チロの行動や気持ちを少し冷静に見ることができるようになる。結果として、チロの行動をユーモラスにとらえることができる。
私たちは物語の読みの中で、同化する読みと異化する読みを無意識のうちに行っている。授業は、それを子どもたちに意識化させていく過程といってもよい。
二つの読みができることが、この作品の読みとしては理想的であるだろう。しかし、無理して二つの読みをさせる必要はない。ただ、チロにより添う読みとチロを少し突きはなす読みの二つの読みがあることを、子どもたちに教えていくのにはふさわしい作品であるといえる。
おわり
プロフィール
- 「読み」の授業研究会 運営委員/関西サークル
- 大和大学
- 2020.09.03研究紀要読み研、研究紀要18号が刊行されました
- 2020.08.04コラム・提言劇場版「ごん」を観る
- 2020.03.07授業づくり『大造じいさんとがん』常体バージョンと敬体バージョンの比較
- 2020.02.25高等学校部会3月1日の高校部会を6月に延期します