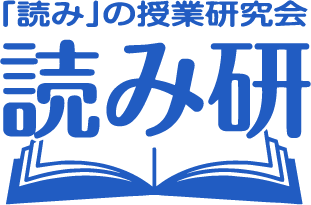「五月雨を集めて早し最上川」(芭蕉)をよむ
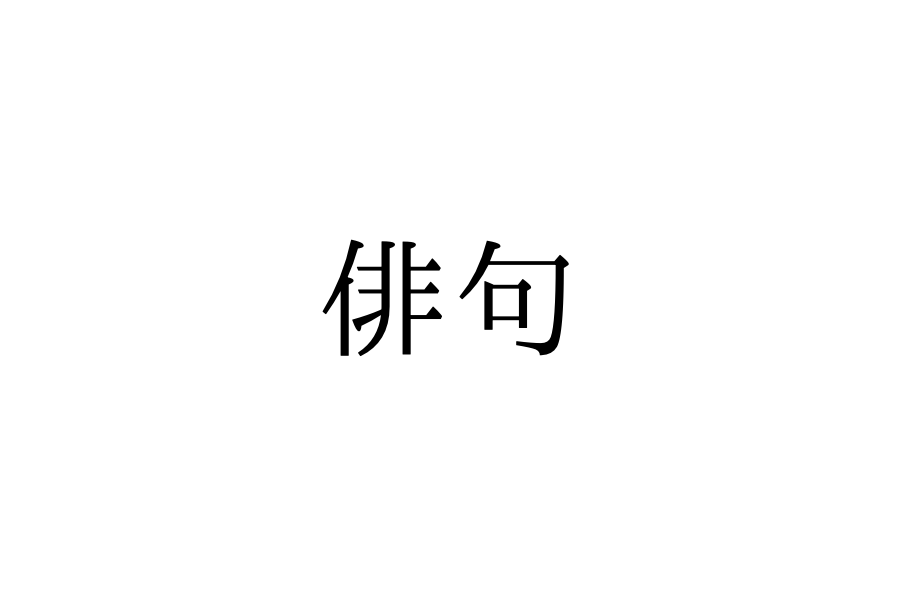
句と地の文を対応させてよむ
湯原 定男(多治見サークル・多治見西高等学校)
この芭蕉の句は人口に膾炙している。私も何度か目にし、芭蕉の句ということは知っていた。だが私自身はそれほどいいなあとは思っていなかった。ああそうか、というところ。
ところが最近「おくのほそ道」全文を読む機会があり、この最上川の句に関してあらためて発見することがあったので報告したい。(既知の方にとっては当然のことかもしれないが)
まずは「最上川」の段全文を引用する。
「最上川は陸奥(みちのく)より出でて、山形を水上(みなかみ)とす。碁点、隼などいふ恐ろしき難所あり。板敷山の北を流れて、果ては酒田の海に入る。左右山覆ひ、茂みの中に舟を下す。これに稲積みたるをや、稲舟とはいふならし。白糸の滝は青葉のひまひまに落ちて、仙人道、岸にのぞみて立つ。水みなぎって舟あやふし。
五月雨を集めて早し最上川 」
一般的に、教科書などに載っているのはこの部分。(といっても掲載しているのはきわめて少ない)ところが、その前「大石田」の段に、こんな表現がある。
「最上川のらんと大石田と云ふ所に日和を待つ。……」
この部分を読み、「なるほど」と腑に落ちた。最上川は単なる川の風景ではなく、実際に芭蕉が「舟に乗った」実感を句にしたものだったのだ。たしかによくみれば「左右山覆ひ、茂みの中に舟をくだす。……」以下は舟に乗った実景である。
とくに「水みなぎって舟あやふし。」がきいている。日和を待っての出発であるから、なんとか舟は出せるようになったものの、水は「みなぎって」いて、まさに「早し」となる。「あやふし」ではないが、その恐怖感が伝わってくるようではないか。
「集めて」も「みなぎる」水の表現としておもしろい。山々に降った五月雨をすべて「集めた」ように感じる水の「早さ」、力感なのだろう。
地の文と対応させて読むことでこの句がダイナミックで動的な句だと理解できる。
「おくのほそ道」のおもしろさは、やはり句と地の文との呼応にもある。
ところで、初稿では「五月雨をあつめて涼し最上川」だったという。大石田で日和を待つ間、地元の俳諧を愛好する人たちと、俳諧連句一巻を巻いたという記述があり、そこでの発句が「涼し」の句だったという。こちらは水を眺めて作ったものだろうか。静的である。
読み比べてみれば、「早し」と「涼し」がわずかに違うだけだが、その表現している世界は明かに異なっている。
■そう思うと、絵巻のこの最上川の絵は、少しのんびりしてないか、などと思えてしまうのですが……。
(奥の細道絵巻-最上川下り ……福島県桑折町・朝日山法圓寺所蔵 )

プロフィール
- 2026.01.28関西地方 2026年3月20日(金・祝日)読み研 関西サークル 学習会
- 2026.01.22春の研究会2026年3月28日(土)「春のスタート講座」開催のお知らせ
- 2025.12.21冬の研究会第40回冬の研究会が本日終了しました!
- 2025.11.06読み研通信『読み研通信』156号が出ました!(無料配信)