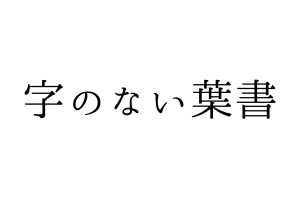メディアリテラシー教育と読みの指導との連携という課題

読み研通信78号(2005.1)
(1)メディアリテラシー教育の展開
メディアリテラシー教育の重要性が、ここのところ強調されてきている。様々な書籍が発行され、発表論文も増えてきている。NIE学会も間もなく発足する。
「リテラシー」とは、「読み書きの能力」のことである。しかし、そういった流れが強くなっているにもかかわらず、「読み書きの能力」を形成するメディアを読むための方法、書くための方法については、必ずしも十分な検討が行われているとは言い難いと、私は見ている。
メディアに親しませるという姿勢やメディアを「読む」ことを指導するという発想は確かにあるのだが、特にメディアを読むことについての具体的な方法については、意外なくらい未解明のままである。また、そのメディアを読むことの指導の中に、メディアの「吟味」「評価」「批判」といった要素が欠落している場合が多くある。
そういう状況の中で、今まで「読み」の授業研究会が追究してきた説明的文章の読みに関する方法論が、大きな役割を果たす可能性があると私は考えている。
特に「事実」をどう読むかということ、「事実」をどのように吟味するかということについての方法論等が、有効に生きてくるはずである。
ここでは、そういった認識を前提に二つの新聞記事を比較・吟味する形のメディア・リテラシー指導を提案する。
(2)同じ出来事についての二つの記事という教材の仕掛け
2000年11月に九州の山中で「ニホンオオカミ」らしき動物が撮影された。2000年11月20日(月)の読売新聞と朝日新聞の記事である。(以下読売をA、朝日をBとする。)
一般的な新聞記事は、「見出し」「リード」「本文」「写真」「キャプション」などから構成されている。それぞれが役割を担いながら記事を構成している。
見出しの吟味から始める。見出しには、「大見出し」「中見出し」など何種類かがある。これらの違いにも着目する必要がある。複数の見出しのうちのどちらを「大見出し」にするかによって、記事全体の効果が違ってくるからである。
まず、「大見出し」から見ていく。
A ニホンオオカミか/九州の山中で撮影
B ニホンオオカミか、野犬か
ともに「か」という不確定の助詞を使っている点では同じである。が、読売が「ニホンオオカミか」とだけ示しているのに対し、朝日は「ニホンオオカミか、野犬か」と「野犬」が入っている。つまり、読売は「ニホンオオカミ」である可能性のみを示しているが、朝日は「ニホンオオカミ」と「野犬」の可能性を並記している。50パーセントずつということであるが、実際には「野犬」である可能性がより前面に押し出されている。
それに対応する形で朝日の「中見出し」は、「九州の山中での目撃騒動」となっている。「騒動」とは「騒ぎ立て(秩序が乱れる)ること」である(『広辞苑』五版)。肯定的な響きをもたない。何か「あまり信憑性のないことで騒いでいる」といったニュアンスまで感じられる。朝日の「中見出し」は、さらに「DNA鑑定にも限界」と否定的なものになっている。
読売の「中見出し」は「『尾の先に特徴』と専門家指摘/『シェパードと類似』異論も」となっている。「専門家指摘」ということは、専門の研究者が「ニホンオオカミ」と認知している可能性を感じさせる。「シェパードと類似」という「異論」を示してはいるが、「異論も」としっかり「も」を付けて「専門家指摘」に比べて「異論」は付加的であるといった印象を受けるような表現になっている。
ここまでで、読売は「ニホンオオカミ」の可能性が大きいことを読者に感じさせる書き方になっているのに対し、朝日は「ニホンオオカミ」の可能性は低いということを読者に感じさせる書き方になっていることが伺える。
次にリード文に行く。「リード文」は、記事の概要を示した前書きにあたる部分である。リード文のすべては紹介できないが、主要な部分は次のとおりである。
A 捕獲されていないため断定はできず、異論もあるが、写真鑑定を依頼された専門家は「ニホンオオカミにほぼ間違いない』との見方を示している。ニホンオオカミと確認されれば、“世紀の発見”だけに、今後の捜査に期待がかかる。
B 数年に一度、思い出したように目撃情報が現れるが、いずれも生息を科学的に証明できる証拠はない。(一文略)本物なら大発見だが、否定的な専門家も多い。
リード文も、見出しに対応して読売は「間違いない」といった「専門家」の評価、「期待がかかる」というコメントなど肯定的な方向のリード文になっている。そして、朝日は「証拠はない」「否定的な専門家も多い」という信憑性を疑う方向のリード文になっている。「専門家」については、相反する矛盾する事実とも読めるが、読売は「鑑定を依頼された専門家」と特定の専門家の評価の引用であり、朝日は「多い」という形で傾向を示している。その意味から、両新聞のいずれかが間違っているとは断定できない。ただし、朝日の「否定的な専門家も多い」の「多い」は、何を持って言いうるのか、現実と対応しているのか、等の検討は必要かもしれない。同時に読売の「期待がかかる」は、「期待」の主体が誰なのかの検討も必要かもしれない。
ここまで「見出し」「リード文」を吟味してきたが、ここでは【語彙・表現の差異を吟味する】【事実の取捨選択の差異を吟味する】といった今まで阿部が提案し読み研で検討を重ねてきた「吟味の方法」を使った。この後の本文の吟味では同じく【事実の取捨選択の差異を吟味する】という方法を使う。ここでは同じように選択された対象であっても、その対象をどの程度の分量でどの程度の具体性で取り上げるかについての差異にも着目する必要がある。(詳しくは、拙著『文章吟味力を鍛える―教科書・メディア・総合の吟味』明治図書を参照願いたい。)
(3)記事本文の比較・吟味
本文の吟味である。
本文の中では、それぞれ複数の「専門家」のコメントを取り上げている。二つの記事で、取り上げている専門家が違う。読売は「背中や足の外側の色が非常に似ている」と話している国立科学博物館の小原氏を取り上げている。それに対して、朝日は「DNAを鑑定しても、断定するのは無理かもしれない」という話している京都大学の相見氏と、「通常は捕獲されないと生息を確認したことにはならない」と話す環境庁野生生物課のコメントを取り上げている。
読売は「ニホンオオカミ」である可能性を支える人物、朝日はそれとは逆の人物を、取り上げている。いずれも、嘘や間違いではない。いずれも「専門家」と言っていい人たちである。誰を取り上げるかの取捨選択の問題である。
二人の人物については、実は読売も朝日もともに取り上げている。元国立科学博物館の今泉氏と東京農工大の、丸山氏である。今泉氏は「ニホンオオカミ」である可能性を示し、丸山氏は可能性の低さを示している人物である。
読売は、「ニホンオオカミ」である可能性を強調している今泉氏のコメント紹介を2・3行を使って行っている。しかし、可能性の低さを表明している丸山氏のコメントは九行だけである。読売の本文は、全部で63行であるから、今泉氏は37%、丸山氏は14%である。
朝日は、可能性の低さを表明している丸山氏のコメントは、42行、可能性の高さを表明している今泉氏のコメントは5行である。朝日の本文は、全部で105行であるから、丸山氏は40%、今泉氏は5%である。
明らかに読売は可能性の高さを強調する方向での取捨選択であり、朝日は低さを強調する方向での取捨選択である。
ちなみに、読売は本文63行、朝日は本文105行というと、朝日の方が重くこの出来事を取り扱っているかのように見える。しかし、実は読売はこの記事を第一面に掲載している。それに対して朝日は、もっと後の「科学」欄に掲載している。その差も吟味する必要がある。明らかに読売の方が大きな扱いである。この日は自民党の加藤紘一氏と山崎拓氏が内閣不信任案に賛成するかどうかでもめているという記事が第一面に掲載されている。そこに並ぶ形で「ニホンオオカミ」を取り上げている。大きな扱いである。
さらには、ここでは検討を省略するが、掲載している写真とそのキャプションにも少なからぬ差異がある。
(4)吟味をリサーチ学習、リライト学習の発展させる
二紙の吟味に続く指導課程として、たとえば記事についてのリサーチ学習が考えられる。この場合であれば、九州で目撃され撮影された動物にかかわる出来事について、様々な方法で子どもたちがリサーチを展開するのである。そのリサーチの後に、それではこの場合は読売と朝日のいずれかの記事がより妥当であったのか、といった評価・検討をしていくことができる。
また、リライト学習も可能である。読売は「ニホンオオカミ」である可能性の高さを窺わせる記事構成、朝日は可能性の低さを窺わせる記事構成であるが、たとえば二紙の「中間」に位置するような記事構成にするとどういう選択や表現が可能であるかを検討し、実際に記事を書かせるのである。これは、大見出し、中見出し、リード文などに絞ってリライトするかたちもある。
仮に読売と朝日の「中間」という想定を授業で行ったとしても、「中間」的な記事の書き方が常に望ましいと、子どもたちに思いこませてしまうことには危険が伴う。記事というものは発信者が明確な観点をもって書いていくことが必要である場合が少なくない。外面的に「中立」に見える記事が一番よいなどという決めつけは、かえってメディア吟味の在り方をゆがめることになる。その時点で外面的に「中立」に見える記事が、実は大きくゆがんでいるという場合も決して少なくないからである。
※以上は、日本国語教育学会編『国語教育研究』384号・2004年4月に掲載の論文を再構成したものである。詳細はそちらを参照いただきたい。
(1)メディアリテラシー教育の展開
メディアリテラシー教育の重要性が、ここのところ強調されてきている。様々な書籍が発行され、発表論文も増えてきている。NIE学会も間もなく発足する。
「リテラシー」とは、「読み書きの能力」のことである。しかし、そういった流れが強くなっているにもかかわらず、「読み書きの能力」を形成するメディアを読むための方法、書くための方法については、必ずしも十分な検討が行われているとは言い難いと、私は見ている。
メディアに親しませるという姿勢やメディアを「読む」ことを指導するという発想は確かにあるのだが、特にメディアを読むことについての具体的な方法については、意外なくらい未解明のままである。また、そのメディアを読むことの指導の中に、メディアの「吟味」「評価」「批判」といった要素が欠落している場合が多くある。
そういう状況の中で、今まで「読み」の授業研究会が追究してきた説明的文章の読みに関する方法論が、大きな役割を果たす可能性があると私は考えている。
特に「事実」をどう読むかということ、「事実」をどのように吟味するかということについての方法論等が、有効に生きてくるはずである。
ここでは、そういった認識を前提に二つの新聞記事を比較・吟味する形のメディア・リテラシー指導を提案する。
(2)同じ出来事についての二つの記事という教材の仕掛け
2000年11月に九州の山中で「ニホンオオカミ」らしき動物が撮影された。2000年11月20日(月)の読売新聞と朝日新聞の記事である。(以下読売をA、朝日をBとする。)
一般的な新聞記事は、「見出し」「リード」「本文」「写真」「キャプション」などから構成されている。それぞれが役割を担いながら記事を構成している。
見出しの吟味から始める。見出しには、「大見出し」「中見出し」など何種類かがある。これらの違いにも着目する必要がある。複数の見出しのうちのどちらを「大見出し」にするかによって、記事全体の効果が違ってくるからである。
まず、「大見出し」から見ていく。
A ニホンオオカミか/九州の山中で撮影
B ニホンオオカミか、野犬か
ともに「か」という不確定の助詞を使っている点では同じである。が、読売が「ニホンオオカミか」とだけ示しているのに対し、朝日は「ニホンオオカミか、野犬か」と「野犬」が入っている。つまり、読売は「ニホンオオカミ」である可能性のみを示しているが、朝日は「ニホンオオカミ」と「野犬」の可能性を並記している。50パーセントずつということであるが、実際には「野犬」である可能性がより前面に押し出されている。
それに対応する形で朝日の「中見出し」は、「九州の山中での目撃騒動」となっている。「騒動」とは「騒ぎ立て(秩序が乱れる)ること」である(『広辞苑』五版)。肯定的な響きをもたない。何か「あまり信憑性のないことで騒いでいる」といったニュアンスまで感じられる。朝日の「中見出し」は、さらに「DNA鑑定にも限界」と否定的なものになっている。
読売の「中見出し」は「『尾の先に特徴』と専門家指摘/『シェパードと類似』異論も」となっている。「専門家指摘」ということは、専門の研究者が「ニホンオオカミ」と認知している可能性を感じさせる。「シェパードと類似」という「異論」を示してはいるが、「異論も」としっかり「も」を付けて「専門家指摘」に比べて「異論」は付加的であるといった印象を受けるような表現になっている。
ここまでで、読売は「ニホンオオカミ」の可能性が大きいことを読者に感じさせる書き方になっているのに対し、朝日は「ニホンオオカミ」の可能性は低いということを読者に感じさせる書き方になっていることが伺える。
次にリード文に行く。「リード文」は、記事の概要を示した前書きにあたる部分である。リード文のすべては紹介できないが、主要な部分は次のとおりである。
A 捕獲されていないため断定はできず、異論もあるが、写真鑑定を依頼された専門家は「ニホンオオカミにほぼ間違いない』との見方を示している。ニホンオオカミと確認されれば、“世紀の発見”だけに、今後の捜査に期待がかかる。
B 数年に一度、思い出したように目撃情報が現れるが、いずれも生息を科学的に証明できる証拠はない。(一文略)本物なら大発見だが、否定的な専門家も多い。
リード文も、見出しに対応して読売は「間違いない」といった「専門家」の評価、「期待がかかる」というコメントなど肯定的な方向のリード文になっている。そして、朝日は「証拠はない」「否定的な専門家も多い」という信憑性を疑う方向のリード文になっている。「専門家」については、相反する矛盾する事実とも読めるが、読売は「鑑定を依頼された専門家」と特定の専門家の評価の引用であり、朝日は「多い」という形で傾向を示している。その意味から、両新聞のいずれかが間違っているとは断定できない。ただし、朝日の「否定的な専門家も多い」の「多い」は、何を持って言いうるのか、現実と対応しているのか、等の検討は必要かもしれない。同時に読売の「期待がかかる」は、「期待」の主体が誰なのかの検討も必要かもしれない。
ここまで「見出し」「リード文」を吟味してきたが、ここでは【語彙・表現の差異を吟味する】【事実の取捨選択の差異を吟味する】といった今まで阿部が提案し読み研で検討を重ねてきた「吟味の方法」を使った。この後の本文の吟味では同じく【事実の取捨選択の差異を吟味する】という方法を使う。ここでは同じように選択された対象であっても、その対象をどの程度の分量でどの程度の具体性で取り上げるかについての差異にも着目する必要がある。(詳しくは、拙著『文章吟味力を鍛える―教科書・メディア・総合の吟味』明治図書を参照願いたい。)
(3)記事本文の比較・吟味
本文の吟味である。
本文の中では、それぞれ複数の「専門家」のコメントを取り上げている。二つの記事で、取り上げている専門家が違う。読売は「背中や足の外側の色が非常に似ている」と話している国立科学博物館の小原氏を取り上げている。それに対して、朝日は「DNAを鑑定しても、断定するのは無理かもしれない」という話している京都大学の相見氏と、「通常は捕獲されないと生息を確認したことにはならない」と話す環境庁野生生物課のコメントを取り上げている。
読売は「ニホンオオカミ」である可能性を支える人物、朝日はそれとは逆の人物を、取り上げている。いずれも、嘘や間違いではない。いずれも「専門家」と言っていい人たちである。誰を取り上げるかの取捨選択の問題である。
二人の人物については、実は読売も朝日もともに取り上げている。元国立科学博物館の今泉氏と東京農工大の、丸山氏である。今泉氏は「ニホンオオカミ」である可能性を示し、丸山氏は可能性の低さを示している人物である。
読売は、「ニホンオオカミ」である可能性を強調している今泉氏のコメント紹介を2・3行を使って行っている。しかし、可能性の低さを表明している丸山氏のコメントは九行だけである。読売の本文は、全部で63行であるから、今泉氏は37%、丸山氏は14%である。
朝日は、可能性の低さを表明している丸山氏のコメントは、42行、可能性の高さを表明している今泉氏のコメントは5行である。朝日の本文は、全部で105行であるから、丸山氏は40%、今泉氏は5%である。
明らかに読売は可能性の高さを強調する方向での取捨選択であり、朝日は低さを強調する方向での取捨選択である。
ちなみに、読売は本文63行、朝日は本文105行というと、朝日の方が重くこの出来事を取り扱っているかのように見える。しかし、実は読売はこの記事を第一面に掲載している。それに対して朝日は、もっと後の「科学」欄に掲載している。その差も吟味する必要がある。明らかに読売の方が大きな扱いである。この日は自民党の加藤紘一氏と山崎拓氏が内閣不信任案に賛成するかどうかでもめているという記事が第一面に掲載されている。そこに並ぶ形で「ニホンオオカミ」を取り上げている。大きな扱いである。
さらには、ここでは検討を省略するが、掲載している写真とそのキャプションにも少なからぬ差異がある。
(4)吟味をリサーチ学習、リライト学習の発展させる
二紙の吟味に続く指導課程として、たとえば記事についてのリサーチ学習が考えられる。この場合であれば、九州で目撃され撮影された動物にかかわる出来事について、様々な方法で子どもたちがリサーチを展開するのである。そのリサーチの後に、それではこの場合は読売と朝日のいずれかの記事がより妥当であったのか、といった評価・検討をしていくことができる。
また、リライト学習も可能である。読売は「ニホンオオカミ」である可能性の高さを窺わせる記事構成、朝日は可能性の低さを窺わせる記事構成であるが、たとえば二紙の「中間」に位置するような記事構成にするとどういう選択や表現が可能であるかを検討し、実際に記事を書かせるのである。これは、大見出し、中見出し、リード文などに絞ってリライトするかたちもある。
仮に読売と朝日の「中間」という想定を授業で行ったとしても、「中間」的な記事の書き方が常に望ましいと、子どもたちに思いこませてしまうことには危険が伴う。記事というものは発信者が明確な観点をもって書いていくことが必要である場合が少なくない。外面的に「中立」に見える記事が一番よいなどという決めつけは、かえってメディア吟味の在り方をゆがめることになる。その時点で外面的に「中立」に見える記事が、実は大きくゆがんでいるという場合も決して少なくないからである。
※以上は、日本国語教育学会編『国語教育研究』384号・2004年4月に掲載の論文を再構成したものである。詳細はそちらを参照いただきたい。
プロフィール