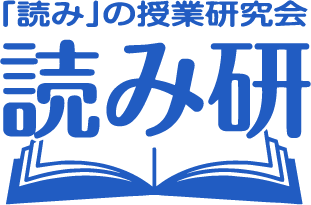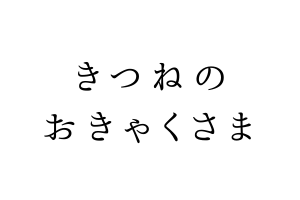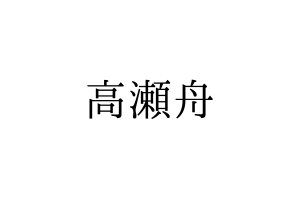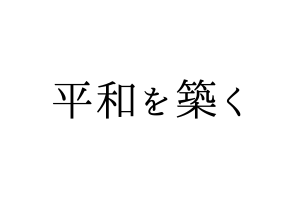「きつねのおきゃくさま」の教材研究
読み研通信85号(2006.10) 橋口みどり(東京・町田サークル) 一、作品について 絵本「きつねのおきゃくさま」の教材化である。話者(語り手)は、昔のお話を聴者(聞き手)である子どもたちに聞かせるように書いたもので […]
徒然草の評価的「吟味読み」
内藤賢司(福岡・矢部中学校) はじめに 運営委員諸氏のすぐれた実践報告がある中で、こんなささいな実践の報告でもいいのだろうかと思いつつ、報告いたします。もうみなさんも実践してあるのかもしれません。それでも、また違った部 […]
導入部の仕掛けからテーマを読む
『高瀬舟』(中3・光村図書)の場合 佐藤建男(運営委員) 小説の導入部に仕掛けられた「仕掛け」を意識的に読むことによって、その小説の通説的に言われているテーマとは別な、新たなテーマが浮かび上がってくることがある。これは […]
国語授業の改革6号 (2006年)
確かな国語力を身につけさせるための授業づくり はじめに OECD(経済協力開発機構)学習到達度調査の「読解力」の結果が悪かったことが、日本で大きな問題として論議されています。 […]
第4回関西サークル例会報告(2006.7.25 京都)
7月25日、キャンパスプラザ京都において第4回例会を開催、9名の参加で教材研究を深めました。 報告1では、松井健氏(立命館守山高等学校)が小説「夢十夜」(夏目漱石)の分析を行いました。この教材は高校1年の教科書(4社 […]
ノート指導「学習記録」
宮城洋之(東京都杉並区立荻窪中学校) ※この実践は大村はま氏の著作にヒントを得たものです。 「読み研方式」を生徒たち自身が理解するようになると、授業に活気が生まれます。それは学習の見通しが立つようになるということと、さま […]
小説「形」(菊池 寛)の指導
小倉泰子(東京都葛飾区立一之台中学校) 中学3年・1学期、短い時間(計4時間)の中での指導を紹介します。 ▼1時間目 1 範読を聞く2 一読後メモを書く(B5版1枚) ①印象に残ったこと ②疑問に思ったこと ③題名「形 […]
子ども向け読み方講座を開いて
読み研通信84号(2006.7) 日浦成夫(東大阪・枚岡西小学校) 採択された教科書や教材の変化とその対応の難しさ 国語の読み方をどのように実践していくかは、その学年の一年間を見通して考えていかなくてはなりません。また […]
授業の中の「言葉かけ」
読み研通信82号(2006.1) 1 むむむっ! 昨年の夏休み、「読み研夏の大会」が行われた時のことです。暑い中、本当にたくさんの方に参加していただき会場は満席となりました。私はその研究会の中のある一つの講座「初心者講 […]
「平和を築く」(三省堂・中3)要旨よみの指導―説明的文章・三読法を生かす実践事例―
読み研通信84号(2006.7) 加納一志(東京・多摩中学校) はじめに――三読法技術の有効活用 三読法(科学的読みの授業研究会がとなえる読解指導法)という有効な指導法を使い、さらに豊かな授業形態はないか、いつも考えて […]