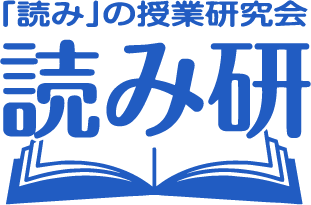話せば→わかる。―添削を口頭で行う―
読み研通信84号(2006.7) 広井 護(土佐高等学校) 一 はじめに 読み研方式を受験指導に応用すると、きわめて有効であることを発見した。実は、「口頭添削」と名付けるすこし変わった受験指導を行っている。文字通り口頭 […]
読み研の研究 実践の緻密な検証と大胆な洗い直しを
読み研通信84号(2006.7) 2006年8月の読み研夏の大会は、二十周年記念大会となる。これまで読み研は、様々な研究・実践上の成果を残してきた。しかし、一方でまだまだ研究・実践上の甘さ・課題も少なからず抱えている。 […]
授業に挑む 詩「相聞」の授業づくり
読み研通信84号(2006.7) 一.学生の教材分析と授業案づくり 教職課程の国語科教育法も後期の大詰めに入って、学生による模擬授業を行うことになった。二クラスとも学習グループは7班編成である。教材は詩、二〇分間の模擬 […]
「見通し」が存在する授業
読み研通信84号(2006.7) 1 お疲れ様でした! 一学期が終了しようとしています。全国の先生方、本当にお疲れ様でした!皆さん、こんにちは。連載3回目となりました。読み研の運営委員、町田です。 わたし達の仕事は、生 […]
文末表現や接続語で段落の中心をつかむ?
高橋喜代治 ―埼玉県の「教育に関する三つの達成目標」パンフの件― 次のテキストをみなさんはどう思われるか。埼玉県教育委員会が昨年4月に出した「教育に関する三つの達成目標」のパンフレットの国語(中一)の説明文の例示である。 […]
生徒会指導に関する提案
高橋喜代治 生き生きとして安定した学校をつくるために 学校が生き生きと安定してあるためには、生徒の集団的・自治的な力(生徒会の存在)が欠かせません。とりわけ、そのリーダー(核)である生徒会本部役員の自覚(自治意識)づく […]
国語科カリキュラムの今昔(その1)
12年以上「今は昔」の話になる。 昔と言えど、毎年、国語科の「カリキュラム」は作らなければならなかった。しかし、作られたカリキュラムは、そのまま“お蔵入り”となる。とにかく、教科書の教材をあらかたこなせば、カリキュラム […]
平野先生の国語通信(その2)
東陵中学校 第三学年国語通信 第三号発行*そろそろテストを作成している平野先生。 腕によりをかけて涙が出るようなものをお送りするので覚悟しておこう。 俳句の読み方 「近代の俳句」の学習で、俳句はビデオより写真に近い表 […]
平野先生の国語通信(その1)
東陵中学校 第三学年国語通信 第一号 発行*二年続けて三年生を担当する平野先生。 心にスイッチを 東井義雄 誰だい?ぼくは 頭は悪いし、ダメな人間かも知れないなんて心配しているのは?ダメな人間なんてあるものか人間は […]
論証責任を問う「批判よみ」のスキル
薄井道正(滋賀県立長浜北高等学校) 拙著『謎とき国語への挑戦』(学文社)に収録した「国語通信」60号で、ロニー・アレキサンダー氏(神戸大学教授)の「『食』だけが文化なのか」(2002年5月23日付『朝日新聞』「eメール […]