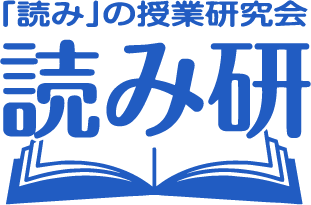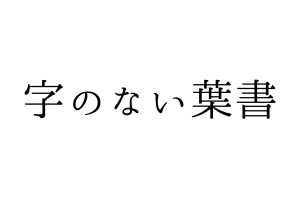教材研究の定説化シリーズ(明治図書)
1 『「一つの花」の読み方指導』(大西忠治編、日浦成夫著、1991年) 2 『「ごんぎつね」の読み方指導』(大西忠治編、小林信次・加藤元康・加藤辰雄著、1991年) 3 『「モチモチの木」の読み方指導』(大西忠治編、小野 […]
大西忠治(読み研創立代表)の著書
大西忠治『大西忠治「教育技術」著作集』全17巻・別巻1(明治図書、1991年) 大西忠治『遊び・イベント上達法』(民衆社、1990年) 大西忠治『討議つくり上達法』(民衆社、1989年) 大西忠治『発問上達法』(民衆社、 […]
国語授業の改革5号(2005年)
国語科 小学校・中学校 新教材の徹底研究と授業づくり はじめに 残念なことですが、ここのところ「読むこと」の指導が不当に軽視されてきたようです。その上、一部には「詳細な読解」指導は、忌避すべきことであるかのような風潮さえ […]
第2回読み研・文芸研合同研究会(2005.6.18-19 東京)
今回のテーマは「文学作品の構造を分析する」です。ストーリーとプロットの関係は? 読み研の「構造よみ」に対して文芸研は? 子どもに指導する際の具体的手立ては? このような点について、両団体が各自の理論・実践をぶつけあいま […]
文芸作品(詩・小説)を教え、学ぶことの意義 ―ヴィゴツキー「美の教育」論に学ぶ―
読み研通信80号(2005.7) 柴田義松(東京大学名誉教授) なぜ詩や小説を教え、学ぶのか 文芸作品で何をどう教え学ぶかについては、西郷竹彦氏や大西忠治氏の研究のおかげで、だいぶんその実質的内容が明らかにされてきた。 […]
「21世紀COEプログラム」国語学力調査報告
2002年に文部科学省が「世界的研究教育拠点の形成のための重点的支援―21世紀COEプログラム」を立ち上げた。そのプログラムにお茶の水女子大学大学院人間文化研究科が「誕生から死までの人間発達科学」をテーマに応募し採択さ […]
教材研究と授業をつなぐもの ─西原さんの疑問に関わって
読み研通信79号(2005.4) 前号で立命館宇治中学高校の西原さんが、読み研方式について次のように述べている。 例えば、説明的文章の「構造よみ」や「論理よみ」では必ずといっていいほど教師同士で意見が対立する。お互い […]
第13回高等学校部会報告(2005.2.19-20 札幌)
第13回高等学校部会報告(2005.2.19-20 札幌) 荒木由紀子(札幌平岡高校) 2月19日(土)~20日(日)の2日間、北海道札幌市の「かでる2・7」を会場に、科学的「読み」の授業研究会第13回高校部会を開催し […]
メディアリテラシー教育と読みの指導との連携という課題
読み研通信78号(2005.1) (1)メディアリテラシー教育の展開 メディアリテラシー教育の重要性が、ここのところ強調されてきている。様々な書籍が発行され、発表論文も増えてきている。NIE学会も間もなく発足する。 「 […]
随筆の構造よみ ─「字のないはがき」─
読み研通信78号(2005.1) 西原丈人(立命館宇治中学校・高等学校) 1 はじめに この原稿を書くにあたって大いに迷った。なぜなら、私は「読み研方式」を踏襲した授業を実践しているわけではない。むしろ「読み研方式」に […]