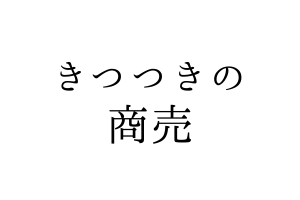「プロット」論─時間と形象に関わって─

研究紀要IV(2002.8)
はじめに
少し前に公開された韓国映画に『ペパーミント・キャンディー』という作品がある。この作品は主人公キム・ヨンホが列車に飛び込んで自殺するところから始まる。そして映画は主人公の過去へと戻って行くのである。このように述べると、よくある語りだしのように思われるかもしれないが、自殺する三日前、五年前、十五年前そして最後は二十年前へと時間は戻っていくのである。キム・ヨンホがなぜ自殺したのか、さらにはどのような青春時代を送ったのかというように、ひたすら過去へとさかのぼる語り口がこの映画の特徴である。過去から現在に向かって語られるのではなく、少しずつ時をさかのぼって語られていく。
過去にさかのぼって語られることは、珍しいことではない。ただ、この作品のように最初から最後まで一貫して過去へとさかのぼっていくという語り方は珍しい。
この作品を見ながら、これはどのように構造よみできるだろうか、と考えた。『ペパーミント・キャンディー』の発端・クライマックスはどこになるのだろう?キム・ヨンホの青春時代から語り出されているならば、クライマックスは彼の自殺のところになるであろう。しかし、前述したように、作品はキム・ヨンホの自殺から始まる。そして過去へとさかのぼる。どう考えても、自殺の場面をクライマックスと考えるのには無理がある。一般的にクライマックスは作品の終わりに近いところに位置するものである。クライマックスが作品の半ばに位置すると、その後の部分は読者(あるいは観客)にとってだれたものになってしまう。しかし『ペパーミント・キャンディー』の場合、過去へ過去へとさかのぼって語られていく。クライマックスが時間的に見てそれまでに語られたことよりも前に起こった出来事ということはあり得ることなのだろうか。しかし、そのように考えないと『ペパーミント・キャンディー』という作品は理解できないだろう。
本論では、映画『ペパーミント・キャンディー』に触発されつつ、小説におけるプロットについてストーリーとの関わりで考えていきたい。
一 『火垂るの墓』(野坂昭如)の時間
『ペパーミント・キャンディー』ほどの極端な時間構成ではないが、野坂昭如の『火垂るの墓』は小説における時間の問題を考えるには興味深い作品である。
この作品はその時間構成から、大きく三つの部分に分けることが出来る。
①昭和二十年九月の三宮駅構内(冒頭~兄と同じ栄養失調症による衰弱死。)
②六月五日の神戸空襲から清太が満池谷を去るまで(六月五日神戸は~そのまま壕にはもどらなかった。)
③清太の埋葬(昭和二十年九月二十二日午後~終わり)
これを時間の順序に並べると、②→①→③となる。読み研方式の構造よみをすると、発端は「六月五日神戸は……」からになる。清太と節子の兄妹が、空襲で母を失い、遠い親戚の家に預けられ、やがてはそこをも追い出され、栄養失調の末死んでいくというのがおおまかなこの作品のストーリーである。とすれば、清太と節子の二人の死に至る道の始まり(すなわち事件の始まり)は空襲で母を失うことからである。ただ一人の保護者である母を失うことから二人の死への道のりがはじまる。とすれば、冒頭(省線三宮駅構内浜側の……)から発端に至るまでの部分は導入部ということになる。
しかし、先ほど述べたようにこの①の部分は時間的順序からすれば発端から始まる一連の事件の最後に来るべきものであり、むしろ終結部と呼ぶにふさわしい部分である。それならば、『火垂るの墓』は終結部が先にあり、それに続いて展開部があるという変則構造になっているといってよいのだろうか?
この問題はすでに「『起承転結』論」(注1)においても述べているので、ここでは結論だけを述べる。アリストテレースの「詩学」によれば、構造の基本は「初め」「中間」「終わり」である。「導入部」は「初め」に「展開部・山場の部」は「中間」に「終結部」は「終わり」に対応する。「終結部」は、作品の終わりに位置するが故に「終結部」と呼ばれるのである。時間的な順序において終わりに位置するから終結部になるのではない。したがって、『火垂るの墓』の①の部分は導入部と考えるべきである。時間的な順序がどうであろうと、作品のはじめに位置している以上それは終結部と呼ぶべきではなく、導入部とすべきである。(注2)
むしろ、ここで問題にすべきなのは、時間的順序からすれば終わりにくるべきものが、作品のはじめにおいて語られていることである。時間の順序を入れ替えて、なぜ冒頭で時間的には終わりに位置する部分が語られるのか、その意味こそが問われなくてはならない。
これまで構造よみにおいてこのような時間構成を問題にするという視点は弱かったのではないか。言いかえれば、構造よみにおいてプロットに目を向けることが弱かったと言えるのではないか。
二 プロット=ストーリーか?
読み研ではこれまで、プロットとストーリーについてどのようにとらえてきたのか。
創立代表である大西忠治の文学作品における読み方理論の集大成ともいえる「文学作品の読み方指導」(注3)では、構造表を図示している中で発端から結末までの部分を「事件の流れ/(筋)ストーリイ/プロット」としている。大西は、「事件の流れ=筋=ストーリイ=プロット」ととらえていたことを示している。
また読み研運営委員会編の「科学的な『読み』の授業入門 文学作品編」(注4) の中でも次のように述べている。
構造よみの中では、事件の流れ(プロット・筋)の始まりである発端と、……
ここでも事件の流れ=プロット=筋であり、したがって構造表における発端から結末までの部分が事件の流れ=プロットというように説明されている。
事件の流れ=プロットであり、発端から結末までがプロットであるとする説明は基本的には大西の理論をそのまま受け継いだものといえる。
大西は一九七九年に「文学作品をどう読ませるか」(注5)で文学作品の読み方指導のあり方を提案した。それに対して、前沢泰が「小説作品をどう読ませるか」(注6)を書いて、大西の提案を評価しつつも、大西の提案にはストーリーとプロットの区別が明らかでないと批判した。その批判に大西は「文学作品の読み方指導をめぐって」(注7)で前沢に答える。
この大西・前沢論争の中で大西は「ストリイとプロットとの統一として考えていく」と述べている。
大西は先の「文学作品の読み方指導をめぐって」で、前沢の論を検討しながら「現在のところ、前沢さんの、ストリイとプロットという概念の導入は、読み方指導においては、あまりメリットがない様に思える」と述べている。そしてそれ以降この問題については大西も読み研もあまり触れてこなかった。わずかに、阿部昇が一九九五年の科学的「読み」の授業研究会第九回夏の大会の基調提案で「ファーブラとシュジェート」の問題を取り上げ、「読み研研究紀要?」の「プロットの転化としてクライマックスを捉え直す」で触れているくらいである。この問題は、読み研全体としてはさほど大きな論議にはなってこなかった。
しかし、先にあげた『ペパーミント・キャンディー』や『火垂るの墓』といった作品を見るならば、プロットとストーリーを統一的にみていくという考え方には限界があるのではないかと私は考えている。
三 プロットとストーリーをどう考えるか
ここで、ストーリーとプロットについて先行の研究を踏まえながら整理しておきたい。
ストーリーもプロットも、調べてみるとその定義は必ずしも明確ではない。
「広辞苑」は次のように述べている。
「ストーリー」①物語。小説。②小説・脚本・映画などの筋または筋書。
「プロット」(小説・脚本などの)筋。筋書。構想。
一般的には、両者はほぼ同じ意味で使われているようである。
E・M・フォスターは二つについて次のように述べている。
「ストーリー」時間の順序に配列された諸事件の叙述
「プロット」諸事件の叙述であるが、重点は因果関係におかれる
そしてストーリーとプロットの違いを次のように説明する。
〈王が亡くなられ、それから王妃が亡くなられた〉といえばストーリーです。〈王が亡くなられ、それから王妃が悲しみのあまり亡くなられた〉といえばプロットです。あるいはまた、〈王妃が亡くなり、誰もまだその理由がわからなかったが、王の崩御を悲しむあまりだということがわかった〉となれば、これは神秘をふくむプロットで、高度の発展を可能とする形式です。それは時間的順序を中断し、その諸制限の許しうるかぎり、ストーリーからはなれています。王妃の死を考えてください。ストーリーならば、〈それからどうした?〉といいます。プロットならば〈なぜか?〉とたずねます。これが小説のこの二つの様相の基本的な違いです。(注8)
このフォスターの因果関係があればプロットだという説明は私には少々わかりにくい。〈王が亡くなられ、それから王妃が亡くなられた〉と〈王が亡くなられ、それから王妃が悲しみのあまり亡くなられた〉とを区別したとして、そのことが作品を読み深めて行く上で大きな意味を持つとは私には思えない。いくつもの事件が描かれている場合、事件と事件をつなぐものとして因果関係が述べられることはありうる。因果関係を全て排除したストーリー、因果関係を含みもつプロットといった区別にどれだけの意味があるのか。因果関係がプロットにとって大きな意味を持っていることは認めるが、それをストーリーとプロットを決定的に分けるものと考えることには賛成できない。
フォスターの定義を受けながら、大岡昇平は次のように述べている。
ストーリーは時間の順序に従って、興味ある事件を物語るだけだが、プロットは物語の順序を、予め「仕組む」ことを意味します。重大な事件は物語の始まる前に起こっていて、或いは最後の章で判明する場合もあります。出来事のすべてを物語るわけではなく、結末に予定されている事件に、関連のあるものだけを書く。最後の章に到って、それらの「伏線」が一つの結末に向かって統一されているのを知って、読者は一種の満足感を味わうのです。(注9)
ストーリーの定義はフォスターとほぼ同じだが、プロットを「仕組む」ことだと大岡は述べる。つまり、どのように語るか、その語り方こそがプロットだと大岡はいうのである。この定義の方がフォスターよりも私にはわかりやすい
また、西郷竹彦は文芸学の立場から筋には二つの規定があるとし、事件の筋をファーブラ、作品の筋をシュジェートと呼ぶ。そして、それぞれを次のように説明している。
ファーブラは、現実の事件の因果関係にもとづく継時的展開。
シュジェートは、文章表現上にあらわれた形象(ものごと)の相関(からみあい)の展開。(注10)
西郷は、ファーブラ(ストーリーと対応させて考えてもよいだろう)の中に因果関係を入れている。西郷の考えには後でふれる。
用語の異なりもあるが、ストーリーとプロットの定義が微妙に食い違っていることは、この三者の引用からでもあきらかであろう。
私はストーリーとプロットについて先行の研究を参考にしながらも、次のように考える。ストーリーとは、時間の順序に従った、語られる事件の素材。プロットは、小説・物語の語られ方、語りの仕掛けと考える。語りの仕掛けという場合、時間的な順序をどうするかということは大きな問題である。が、それ以外にも事件をどのように語るか、理由(または心理)から語るのか、行動から語るのか、あるいは何を中心に語るのかといったさまざまなことが考えられる。それらを全て含めてどのように語るかその語られ方をプロットと私は考える。(注11)フォスターは因果関係に重点をおいて両者を考えたが、因果関係の有無で両者を区別するよりも、ストーリーを時間の順序に従った、語られるべき事件の素材、それをどう語るかがプロットと考えた方が作品分析においては有効だと考える。
つまり、ストーリーだけでは作品は成立しない。そのストーリーをどのように語るかという仕掛け(プロット)があって、はじめて作品として成立するのである。
大西は「文学作品の読み方指導をめぐって」で前沢のプロットについての考えを批判して次のように述べる。
①「筋」における「プロット」、②作品構造における「プロット」、③形象相互における「プロット」という、三つの次元の異なった考えが、前沢さんの提言には混在していると思われるのである。
大西の言うようにプロットという時、そこにはいろいろな意味合いが込められている。したがってプロットという一語で片づけるのではなく、プロットのどのような側面についての論及なのかを踏まえておく必要がある。
プロットには様々な側面があるが、私は主として二つの側面について踏まえておくことが重要だと考えている。一つは、作品をどこから語り始め、どのような順序で語っていくかという、主として時間軸に関わる問題である。(別の場所で同時間帯で起こったことを語る場合には、どの出来事から語るかという場所の問題となることもある)例えば、『火垂るの墓』『蘭』(竹西寛子)『六月の蝿取り紙』(ねじめ正一)などの作品群はこの時間軸の問題が大きな意味を持っているといえる。
もう一つは、どのように語るか(いわゆる書かれ方)という問題である。大西のまとめによれば形象相互における「プロット」といえる。阿部が読み研紀要三号で触れたプロットの問題も主として形象相互の関わりとしての問題であった。
もちろんこの二つの側面はまったく切り離されて存在するのではない。相互に密接に関わりながら存在している。ただ、プロットを考えていく場合、どこに重点をおいて述べているのかはっきりしないと議論は混乱してしまう恐れがある。(注12)
先にあげた西郷は、ファーブラとシュジェートの関係を次のように述べている。
形象相関の展開としてあらわされる筋(シュジェート)の裏に読者は、現実の事件の因果関係をあらわす筋(ファーブラ)を実は読みとって文芸(虚構)の時間を生きているのです。(注13)
西郷の言う「形象相関の展開としてあらわされる筋(シュジェート)の裏に読者は、現実の事件の因果関係をあらわす筋(ファーブラ)を実は読みとって文芸(虚構)の時間を生きている」は明解であり、小説の読み方としてはその通りであると納得できる。だが、読み方を生徒のものにしていく、すなわち読み方教育という観点からとらえると、それだけですませられないものがあるのではないか。シュジェートの裏にファーブラを読むことは、高度な内容を生徒にいきなり要求するものになっていはしないか。書かれている順序にしたがってというのは、ある程度力のある生徒にとってはよいかもしれないが、そうでない生徒にすれば先の見えない、どう進んでいったらよいのかが見えない部分がありはしないか。「形象相関の展開としてあらわされる筋」をどのように読んでいくのか、シュジェートの裏に、現実の事件の因果関係をあらわす筋(ファーブラ)を読みとるとはどういうことかもっと細かく明らかにすべきではなかったか。
西郷はシュジェートとファーブラの関係を明らかにしたが、それを子供たちにどのように読み取らせていくかという点では不充分さを残した。そこに西郷の理論が実践の中で生かされなかった弱さがあるのではないか。
四 『火垂るの墓』の時間の仕掛けを読む
私は『火垂るの墓』の最初の部分を終結部とは呼ばずに導入部と呼ぶと述べた。しかし、導入部で既に事件は終わりを迎えていることも確かなのである。導入部でありながら、事件は終わりを迎えているのが『火垂るの墓』の特徴なのである。大西の規定によれば「事件の流れ=筋=ストーリイ=プロット」であり、それは発端から結末までのいわゆる展開部と山場の部をさす。しかし、『火垂るの墓』の導入部を、事件の流れからはずして考えていくことは、事件の中に清太の死を含めないことにもなり、明らかにおかしなことになる。
『火垂るの墓』の冒頭において、主人公清太の死が、まず語られるのである。続けて妹節子の死も説明される。物語の冒頭において、物語の結末がはっきりと示されてしまう。そのことが持つ意味こそが問題にされなくてはならない。そしてそこに目を向けるためには作品のプロット(この場合は時間軸における)を読むという観点が重要になってくる。
通常、読者は主人公に寄り添いながら、その運命がどうなるかに興味を抱きつつ物語を読み進めて行く。清太は生き延びられるのだろうか。節子はなんとしても助かって欲しい。そんな思いを読者は持ちながら、主人公に寄り添いながら物語を読み進める。そこに、物語を読む面白さもあるといえよう。ところが、『火垂るの墓』ではそのような興味はまず初めに失われてしまう。清太も節子も死ぬのである。
『火垂るの墓』には主人公に寄り添って運命をともにしていくといった面白さはない。物語の結末がはっきりと示されている以上、結末を予想したり、そこに期待したりすることはできない。もう、すべての出来事は終わってしまったのだ。
主人公・清太の死が、冒頭において語られる。人の死であるだけに、その衝撃は大きい。それが読者を作品の世界に引き込む大きな力になっている。
しかし、このことは『火垂るの墓』という作品の弱点にも成りかねない。二人の運命がどうなるか、そこに読者の関心もある。しかし、最初に結末ともいえる二人の死を示すことは、二人がどうなるのかという興味関心で作品を読むことをはじめから期待していないことになる。その意味で、『火垂るの墓』はストーリー的な面白さを、初めから捨て去っているのである。
ストーリー的な面白さをなぜ『火垂るの墓』はあえて、捨て去るのか。なぜ、清太の死というドラマチックなところから語り始めるのか。そこに『火垂るの墓』を読み取るカギがある。言いかえればそれこそが『火垂るの墓』の語りの仕掛けを読み解くことになるのである。
清太の死から語り始めることは、結末を見せてしまうだけに、この先どうなるのかという期待を読者に持たせることはできない。その代わりに、なぜ清太が死んだのか、あるいは死ななくてはならなかったのかという疑問を持たせることになる。当然、その後の展開はその疑問に答えることになっていく。つまり、語る内容が質的に変化するのである。「次はどうなる」ではなくて、「なぜ」が語りの中心に位置するのである。
また、結末を先に示すことは、結末そのものにさしたる意外性がないということでもある。『火垂るの墓』は戦争の中で清太と節子の二人の子どもが二人だけで生きていこうとする話である。しかし、戦争の時代は、子どもだけで生きぬけるほど甘いものではない。戦争の中での子どもの運命などは語る前からわかっている、そういった語り手の認識のあらわれが、最初に清太の死を示すことになったのではないか。
そして、『火垂るの墓』の場合清太や節子の死が初めに語られることから、作品のクライマックスそのものの持つ意味も変化しているといえる。前述したように清太と節子の運命がどうなるのかといった興味関心で『火垂るの墓』は語られるのではない。二人はなぜ死ななくてはならなかったかといった「なぜ?」が語りの中心になる。なおかつその「なぜ?」に向かって一気に語られていくというのではない。二人の死が栄養失調による衰弱死であることに明らかなように、死は徐々に二人に訪れていく。一歩一歩二人は死へ近づいていく。その意味では、死への決定的なひきがねになったというところがわかりにくい。つまり、クライマックスがはっきりしない作品といえる。
私は『火垂るの墓』のクライマックスをしいてあげるならば、節子の死の場面ではないかと考えている。しかしこの場面も、「八月二十二日昼、貯水池で泳いで壕へもどると、節子は死んでいた。」とあっさりと説明されているだけなのである。その後に続く文は、二、三日前の節子の様子である。節子の死で作品が盛りあがるようには書かれていないのである。
このように、どのような時間の順序で語るかという問題は、作品の構造そのものにも大きく関わる問題になっている。そして、そこに着目することで作品そのものが読めてくるのである。
五 形象としてのプロット
『火垂るの墓』に対して、『羅生門』は作品全体としておおむね時間の順序に叙述された作品といえるが、全てそうなっているわけではない。主人公の下人は「主人からは、四五日前に暇を出された」と述べられる。しかし『羅生門』の事件は、下人が主人から暇を出されたから、羅生門の上で老婆と出会い、その着物を剥いで去って行ったというようには書かれていない。主人から暇を出された下人が羅生門にやってくる事には何ら必然性がない。もちろん主人から暇を出されなければ、羅生門にいることもないわけだが、主人から暇を出された下人がすべて羅生門にやってくるものでもない。この下人が羅生門にいるのは、たまたま羅生門の近くで雨に降られたからにすぎない。雨やみのために羅生門にいるのである。「或日の暮方の事である。一人の下人が、羅生門の下で雨やみを待つてゐた。」という冒頭の記述が示すとおり、作品のはじまりから下人は羅生門の下にいるのである。「四五日前に暇を出された」ことと下人が羅生門の楼の上で老婆と出会う事件とは必然的に結びつくようには語られてはいないのである。したがって、
◎四五日前に暇を出された
◎羅生門の下で雨やみ
◎羅生門の楼の上にのぼる
◎老婆と出会う
といったように時間的に並べ直してみたところで、『羅生門』の事件の筋をとらえたことにはならない。問題は、作品の中で何が主要なものとして語られているか、つまり語りの仕掛けを読み取らなくては『羅生門』の主要な事件の筋は見えてこないのである。
先ほども引用したように、下人は作品のはじめから羅生門の下にいる。そして「下人は七段ある石段の一番上の段に、洗ひざらした紺の襖の尻を据ゑて、右の頬に出来た、大きな面皰を気にしながら、ぼんやり、雨のふるのを眺めてゐ」るのである。「下人は、大きな嚔をして」と述べられるまで、下人の動きは何一つ語られていない。何故下人が羅生門に居るか、京の都の様子や羅生門の荒れ果てていること、下人のこれまでの境遇、そして今置かれている下人の状況、さらには今下人が考えていることなどが次々と説明される。下人はただ、石段に腰を下ろしているだけなのである。ところが大きな嚔の後は違う。「大儀そうに立上が」り、「門のまはりを見まはし」、「上の楼へ上る、幅の広い、これも丹を塗つた梯子」を見つけ、上の楼へと上っていく。下人は積極的とは言えないまでも、行動的である。そしてその行動の結果として老婆と出会うのである。偶然ではあるにせよ、上の楼へ上っていくからこそ、下人は老婆と出会うのであり、楼に上っていかなかったとすれば、下人と老婆の出会いはない。下人が羅生門に居るだけでは、何も事件は起こらないのである。いや正しくは、下人が羅生門に居るだけでは、何ら変わりのない日常がただ過ぎてゆくだけのことであり、そこに事件性など何一つない様に語られているのが『羅生門』なのである。そのような語りの仕掛けを読んでいってこそ、『羅生門』での事件が下人と老婆の二人を中心に起こることがはっきりするのである。
つまり、『羅生門』の構造を読んで行くことは、『羅生門』の語りの仕掛け(プロット)を読むことなしには出来ないのである。ただ単に、出来事を時間の順序に並べてみるだけでは、何がそこにおける主要な事件かは見えてこないのである。
おわりに
一つの作品が語られようとする時、その時点において、事件は既に終わってしまっている。これから起こる事件が語られるのではない。既に終わってしまった事件が語られるのである。語り手は、どのようにその事件を語るのかという語り手なりの問題意識を持って語る。決して、行き当たりばったりには語らない。どのような順序で、どのような事件として、どのように語るのか、それらはすべてプロットの問題である。
『火垂るの墓』のストーリーは昭和二十年九月の清太の死から語り始めようと、時間の順序に従って六月五日の神戸空襲から語り始めようと変わらない。どちらにせよ、前述したように「清太と節子の兄妹が、空襲で母を失い、遠い親戚の家に預けられ、やがてはそこをも追い出され、栄養失調の末死んでいく」というストーリーに変化はない。では小説作品として同じであるかといえば、答えは明らかにノーである。
どのような時間の順序において、いかに語るかということは作品そのものの成立に大きく関わっているといわざるを得ない。ストーリーとプロットとを同一のものと見なしていくところからは、作品をこのような視点から読み解くことは見えてこない。
はじめに取り上げた『ペパーミント・キャンディー』においてもそうである。継時的に事件の流れをとらえていくという観点からは、この作品は理解できない。重要なことは、どのように語られているか、つまりプロットの読み取りなのである。
構造よみにおいても、そこにどのような事件が語られているかということは、当然読み取るべきことであるが、より重要なことはそれがどのように語られているかというプロットを意識した読み方なのである。そのような観点から『ペパーミント・キャンディー』を読んでいくならば、過去へさかのぼって語られていくということは、構造よみにとって何ら支障がないことがはっきりするだろう。
最後に、実践的な問題に一言ふれておく。プロットを読むことの重要性を述べてきたが、小学校の低・中学年においての指導や構造よみの導入段階では、いきなり、プロットに目を向けさせていくことは難しい。指導の段階としては、ストーリーをきちんと読み取らせる指導の上に、プロットを読み取る過程が位置づくことは確認しておきたい。
注1 科学的「読み」の授業研究会「研究紀要」? 二〇〇一年八月
注2 導入部がなく、いきなり展開部から作品が語り出されているような構造はありえる。ここで問題としているのは、発端以前の部分を、その時間的な順序に関わらず、導入部と呼ぶことを述べているのである。
注3 明治図書 一九八八年
注4 東洋館出版社・二〇〇〇年 この著作は、読み研運営委員会の編著としては一番新しいものであり、運営委員会として合意された「公的な」読み研理論ということが出来よう。
注5「生活指導」一九七九年一月号
注6「生活指導」一九七九年六月号・七月号
注7「生活指導」一九七九年十二月号
注8 E・M・フォスター「新訳 小説とは何か」ダヴィッド社 一九六九年
注9 大岡昇平「現代小説作法」 大岡昇平全集第十二巻 中央公論社 一九七四年
注10 西郷竹彦文芸教育著作集 第17巻一四三ページ 明治図書 一九七五年
注11 阿部昇は先に引用した「プロットの転化としてクライマックスを捉え直す」の中で「ストーリーを〈自然の時間の順序に従って動いていく出来事のつながり〉、プロットを〈ストーリーを素材として取捨選択され連関させられ仕組まれ形象化された作品そのもの〉」と定義している。私の考えもこれに近い。
注12 プロットについて考える場合、これ以外にも誰が語っているかという話者の問題、どのような形式で語るかという問題などがある。が、それらは話者や形式の問題として別に論じることも可能なので、本論では触れない。
注13 西郷竹彦文芸教育著作集 第巻一四六ページ 明治図書 一九七五年
プロフィール
- 「読み」の授業研究会 運営委員/関西サークル
- 大和大学
- 2020.09.03研究紀要読み研、研究紀要18号が刊行されました
- 2020.08.04コラム・提言劇場版「ごん」を観る
- 2020.03.07授業づくり『大造じいさんとがん』常体バージョンと敬体バージョンの比較
- 2020.02.25高等学校部会3月1日の高校部会を6月に延期します