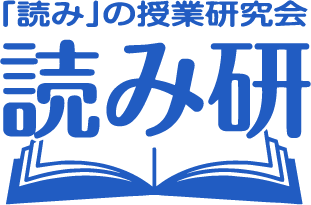説明的文章「動物の体」(東京書籍・小学五年)の教材研究
1.構造よみ 前文 1段落本文 1 2~6段落 (動物の体の形と気候との関係) 2 7~9段落 (動物の体格と気候の関係) 3 10~13段落 (動物の毛皮の役目) 4 14~21段落 (ラクダの体の仕組 […]
第9回関西サークル例会報告(2007.11.17 大阪)
11月17日に9回目の例会をもちました。参加者は7名でしたが、関西サークルが少しずつ定着してきていることを実感できる内容でした。神戸の永田彰さんと加藤で『白いぼうし』の実践と教材研究の報告、豊中の児玉健太郎さんから中学 […]
「読み」の授業の中でのスポット文法のすすめ(2)
読み研通信89号(2007.10) 前回に引き続き、読みの授業の中でスポット的に文法を扱うことで作品の理解が深まるような場面を提案したい。 1 「トロッコ」(芥川龍之介)の終結部から 「トロッコ」は、八歳 […]
PISA「読解力」およびCOE「読解力」と読み研
読み研通信89号(2007.10) 一 PISA「読解力」・COE「読解力」に共通する日本の弱点 二○○三年にOECD(経済協力開発機構)が実施したPISA(生徒の学習到達度調査)の結果が、二○○四年に公表された。それ […]
第8回関西サークル例会報告(2007.9.22 大阪)
今回取り扱う教材が全て高校教材であったにもかかわらず、小中の教員も含め11名の参加者で充実した研究会となりました。 最初に、高槻中学高等学校の竹田博雄先生の分析報告「こころの情報学」(高校1年評論・西垣通)を検討しまし […]
「竹取物語」の冒頭部分を読む
内藤賢司(運営委員) 私の、次のような小さな読みの試みでも、古典の読みのおもしろさが生徒たちに広がった。その実践を次に報告します。 「竹取物語」の冒頭部分(教科書掲載部分)を、小説・物語の導入部を読む指標で読んでみたい […]
国語授業の改革7号(2007年)
教材研究を国語の授業づくりにどう生かすか 中央教育審議会はじめ様々な場で「読解力」向上が叫ばれ「読むこと」の指導が見直されようとしています。また、「確かな学力」の育成、到達目標的な教科指導のあり方も強調されつつあります。 […]
「自分の意見」を述べるための指導
「読むこと」から「書くこと」へ 宮城洋之(東京都杉並区立荻窪中学校) 1.2つのハードル 「書くこと」の授業で、なかなか書き出せない生徒や、書き始めたのは良いけれど途中で立ち往生してしまう生徒っていませんか。「書くこと […]
第7回関西サークル例会報告(2007.6.16 大阪)
6月16日(土)、7名の参加で例会を開催し、教材分析の検討を行いました。 (1) 小説「やまなし」(宮沢賢治、光村小6) 提案 永田 彰(神戸市立広陵小学校) 永田さんは昨年の夏の大会が読み研初参加です。「やまなし」 […]