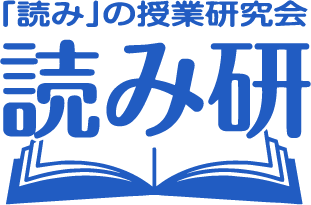菊池寛『形』の指導
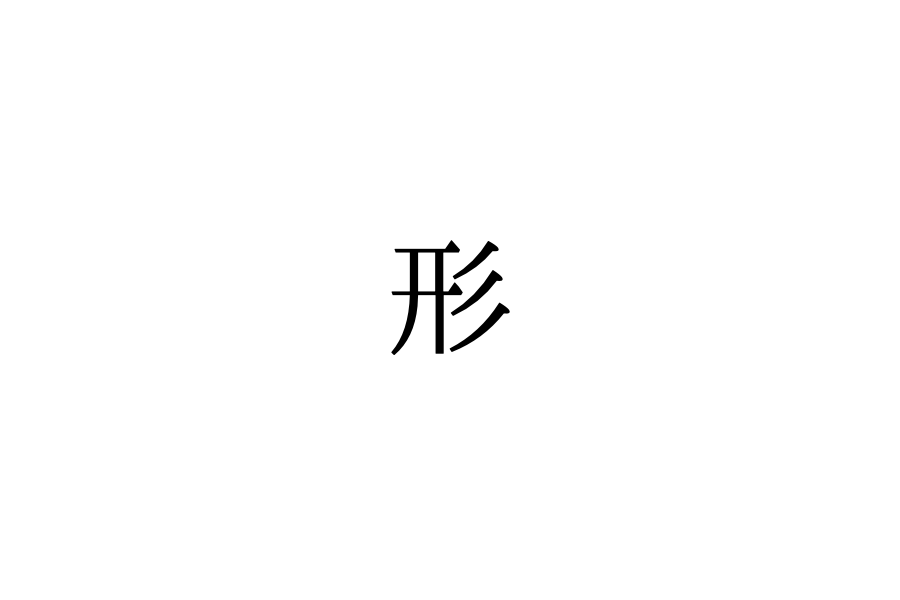
(1)『形』の事件について
『形』は中学校3年の教科書(三省堂)に収録されている菊池寛の作品である。
戦国時代、摂津半国の侍大将であった中村新兵衛は、五畿内、中国に聞こえた槍遣いの名手であり、「槍中村」の異名をもっていた。三間柄の大身の槍をあやつり、先駆けしんがりの功名を重ねる新兵衛は、自他共に認める実力者であった。さらに、彼のシンボルとも言える「猩々緋の羽織」と「唐冠纓金のかぶと」は、敵味方にとって脅威や信頼の象徴として定着していた。そんな中、新兵衛が守役として慈しみ育ててきた「若い侍」に請われ、その「猩々緋の羽織」と「唐冠纓金のかぶと」を快く貸してしまう。そして、明くる日の戦いの場で、いつもとは違うかぶとを身につけた新兵衛は命を落としてしまうのである。
「形」が時として独自のはたらきを、それも実力以上のはたらきをすることや、「内実」ではない「形」に惑わされることは、私たちの日常生活でも経験することがある。新兵衛がそのことに初めて思い当たったその瞬間に、彼の最も得意とする槍によって命を奪われるという皮肉な結末は衝撃的である。
この作品のクライマックスは、最後の一文「敵の突き出した槍が、縅の裏をかいて、彼の脾腹を貫いていた。」である。ちなみにこの作品の構造上の特徴は、「終結部」がないことであり、クライマックスで作品が終わっていることの効果は大きい。
クライマックスからこの作品を読むと、二つの勢力が浮かび上がってくる。つまり、中村新兵衛の槍の遣い手としての「内実、実力」と、その実力と相まって力を持ち始めたシンボルとしての「形」の二つである。逆にその二つの勢力が転化、確定したところをクライマックスとするのだが、この作品の事件は、「形」の力に対する認識の薄かった新兵衛が、「形」の力にどう気づくかというプロットで展開していく。つまり、展開部や山場の部ではどこを読むべきかが見えてくる。
(2)導入部における「事件設定」のとらえ方
導入部は、「時・場・人物・事件設定」を読む。人物では「中村新兵衛についてわかる言葉を探してみよう」と指示を出す。すると、前半に出てくる「侍大将」「五畿内、中国に聞こえた大豪の士」「槍中村」「三間柄の大身の槍」「先駆けしんがりの功名」と、後半に登場する「猩々緋の羽織」「唐冠纓金のかぶと」が「実力」と「形」という構図で対比させてあることが見えてくる。ここに書かれ方の工夫がある。
私は「事件設定」をこうとらえる。すなわち小説(物語)にはしかけ(伏線)があり、それを読み取らせる。ここでは、「内実、実力」に対比される「形」(外面、格好)が導入部の中で強調されており、その書かれ方に着目させる。
まず、「形」についての記述が多い。導入部の記述は、教科書で18行だが、前半の「実力」については7行半、後半の「形」については11行半と、「形」についての記述が多いことがわかる。
次に、くり返しの表現がある。「水ぎわだった華やかさ」「輝くばかりの鮮やかさ」と「猩々緋の羽織」と「唐冠纓金のかぶと」の存在感がアピールされる。
さらに、対句表現で「猩々緋の羽織」と「唐冠纓金のかぶと」が描かれる。
味方が崩れ立ったとき、激浪の中に立つ巌のように、敵勢を支えている猩々緋の姿は、どれほど味方にとって、頼もしいものであったかわからなかった。
また、嵐のように敵陣に殺到するとき、その先頭に輝いている唐冠のかぶとは、敵にとって、どれほどの脅威であるかわからなかった。
傍線部は、直喩法を使って、「猩々緋の姿」の盤石であることを表現している。
そして最後に「槍中村の猩々緋と唐冠纓金のかぶとは」と主語を置きかえる。つまり、導入部ですでにこの物語の主体は「形」にあることを書き方で示しているのである。
(3)展開部と山場の部の形象よみ
展開部では「実力」と「形」が絡み合いながら事件が展開するところに着目する。ここでは「形」では、その力に頼ろうとする若い侍の言葉「・・・なんぞ華々しい手柄をしてみたい」「あの羽織とかぶととを着て、敵の目を驚かしてみとうござる」を読む。「なんぞ」「驚かして」という表現から、若い侍が決定的で永続的な勝利を望んで請うたものではなく、あくまでも「初陣ゆえの」一時的な願いであったのである。だから、新兵衛も「快く受け入れることが」できた。
また、「実力」では、新兵衛の「念もないことじゃ」「あの羽織やかぶとは、申さば中村新兵衛の形じゃわ。」「我らほどの肝魂をもたいでは、かなわぬことぞ。」を読む。ここでは、形はあくまで形であり、形を重視せず、内実・実力を重んじる新兵衛の考えが読める。
山場の部では、「形」を重視していなかった新兵衛の心の変化に着目して読む。授業では3カ所と指定して探させた。
①そして、自分の形だけすら、これほどの力をもっているということに、かなり大きい誇りをかんじていた。・・・「自分の形だけすら」から読めるのは、自分の実力に対する揺るがない自信であり、勝利への確信であり、ましてや自分が槍で負けるなどとは微塵も考えていない。
②彼は、二番槍は自分が合わそうと思ったので、駒を乗り出すと、一文字に敵陣に殺到した。・・・「二番槍は自分が」「一文字に」という表現からも新兵衛の揺るがない自信が読める。「形」を借りた若武者が「大きく輪乗り」をして攻め入ったのとは対照的である。
③手軽にかぶとや猩々緋を貸したことを、後悔するような感じが頭の中をかすめたときであった。・・・「後悔するような感じ」で初めて「形」が持っていた力に気づく。「気づく」というには、あまりにも淡々とした嫌な予感がよぎったということである。でも時すでに遅く、それも脾腹を貫かれるという完璧なやられ方、確実な死を予想させる結末を迎えてしまう。
(4)終わりに
主題は次のようにまとめた。
「形」は時として「内実・実力」以上の独自のはたらきをすることがある。
人間は時として「形」に惑わされてしまうものである。
プロフィール
- 「読み」の授業研究会 運営委員/福岡八女サークル
-
八女市立見崎中学校
[趣味]テニス
[執筆記事]教育科学「国語教育」(明治図書)
№860(2021年8月)中学校 教科書「新教材」の教材分析・授業ガイド「クマゼミ増加の原因を探る」(光村図書2年)
№845(2020年5月)定番教材で学ぶ!場面別 説明文の指導技術・ 交流・話し合いの技術「クジラの飲み水」
№812(2017年8月)中学校 教材研究のポイントと言語活動アイデア 「モアイは語る」ー[全体を俯瞰する][詳しく見る][吟味する]
№751(2013年6月)文学作品指導における〝価値ある発問〟の具体例 比喩・反復などの表現技法をとらえさせる 他
- 2020.11.01国語授業講座Q&A【国語授業実践講座 Q&A】読み研(方式)って、成績の良い児童(生徒)の学校だからできるんでしょう?
- 2014.03.03教材研究構造よみの指導~「小さな手袋」(内海隆一郎) 三省堂・中学二年~
- 2012.04.03教材研究『竹取物語』を読む
- 2009.06.25教材研究「小さな手袋」(内海隆一郎:中2「三省堂」)の導入部を読む